自分用メモ。一昨年、昨年と同様に、民俗学者キャラクターでこの一年を振り返るという相変わらずよくわからない趣旨の記事だ。
昨年の記事↓
【メモ】民俗学者キャラクターまとめで一年を振り返る2022 - 猫は太陽の夢を見るか:番外地
というわけで、今年2023年に発表されたマンガ、アニメ、映画、ドラマ、ゲーム、小説等のうち、民俗学者キャラクターが出ている作品を、時系列順に以下に一覧化した。この場合の「民俗学者キャラクター」とは、フィクションに登場する民俗学者や民俗学の学生、あるいは作品の中で「民俗学に詳しい」と思われる描写のある「民俗学者っぽい」キャラクターのことを指す。今回は一昨年、昨年とは変えて、シンプルにタイトルだけを並べてみた。
民俗学者キャラクター登場作品一覧2023
1月
5日 [マンガ]吉元ますめ「くまみこ 第一一一話「異変」」『月刊 コミックフラッパー』2023年2月号(KADOKAWA)
12日 [ゲーム]オンラインゲーム『Sailing Era(セーリング エラ)』(bilibili)、スマートフォン向けゲームアプリ『IdentityV 第五人格』(NetEase Games)春節イベント2023「戯楽で旧年を辞し 粉墨で新年を描く」
10日 [小説]庵乃音人『桃色の未亡人村』(悦文庫)
15日 [マンガ]三国ハヂメ『佐倉叶にはヒミツがある 3』(白泉社、※電子版のみ)
17日 [小説] 高田崇史『試験に出ないQED異聞 高田崇史短編集』(講談社文庫)
18日 [小説]朝宮運河 編・著『てのひら怪談 見てはいけない』(ポプラキミノベル)
25日 [小説]谷尾銀『ゆるコワ! ~無敵のJKが心霊スポットに凸しまくる~』(角川文庫)、杜宮花歩『怪異学専攻助手の日常 蓮城京太郎の幽世カルテ』(メディアワークス文庫)、岡田遥『妖怪の遺書、あつめてます』(メディアワークス文庫)、鉈手璃彩子『鬼妃 ~「愛してる」は、怖いこと~』(メディアワークス文庫)、宮澤伊織『裏世界ピクニック8 共犯者の終り』(ハヤカワ文庫JA)
26日 [小説]波摘 著, noprops,黒田研二 原作『青鬼 調査クラブ 7 怪物を従えた少女と激突せよ!』(PHPジュニアノベル)
30日 [小説]萩原麻里『人形島の殺人 呪殺島秘録』(新潮文庫nex)
2月
3日 [ドラマ]『A2Z』(共同テレビ、Amazon Prime Video)
7日 [小説]柊坂明日子 著, 三雲百夏 監修・原案『一教授はみえるんです 京の都は開運大吉!』(小学館文庫キャラブン!)
8日 [小説]秋木真『怪盗レッド23 織戸恭也のひそかな想い☆の巻』(角川つばさ文庫)
10日 [映画]『呪呪呪 死者をあやつるもの(原題:謗法: 在此矣、방법: 재차의、The Cursed: Dead Man's Prey)』(ハピネットファントム・スタジオ)
13日 [小説]櫻田智也『蝉かえる』(創元推理文庫)
15日 [マンガ]戸川四餡「黒巫鏡談」第一話『ハルタ』Vol.101(KADOKAWA) / [CM]スペシャルムービー『Wpc.2023 春夏物語 雨と傘と蛙亭』(ワールドパーティー) / [小説]時田とおる『あやかしの食事処 怪し怖しは蜜の味』(富士見L文庫)、都市伝説探偵事務所 編『都市伝説探偵セツナ 超常Xファイル』(ポプラ社)
16日 [小説]相川真『京都伏見は水神さまのいたはるところ ふたりの春と翡翠の空』(集英社オレンジ文庫)
17日 [マンガ]Batta『狐のお嫁ちゃんと息子ちゃん 2』(eBookJapan Plus、※電子版のみ)
21日 [小説]安田依央『出張料亭おりおり堂 あつあつ鍋焼きうどんと二人の船出』(中公文庫)、三國月々子『ナゾノベル 鬼切の子 1 異界から来た少年』(朝日新聞出版)
25日 [マンガ]星野之宣「宗像教授世界篇」第一話『ビッグコミック』第5号 2023年3/10号(小学館)
28日 [マンガ]吉川景都『こまったやつら ~民俗学研究会へようこそ~ 3』(少年画報社)
3月
1日 [マンガ]三国ハヂメ『佐倉叶にはヒミツがある 4』(白泉社、※電子版のみ。コミックシーモア、Renta!、ebookjapanでは2月15日に先行配信)
8日 [小説]芦花公園『パライソのどん底』(幻冬舎)、一ノ瀬三葉『時間割男子 11 つなげ! 100点満点のきずな』(角川つばさ文庫)
9日 [小説]白川紺子『京都くれなゐ荘奇譚 三 霧雨に恋は呪う』(PHP文芸文庫)
17日 [小説]ツカサ『お兄様は、怪物を愛せる探偵ですか?』(ガガガ文庫)
22日 [小説]澤村御影『准教授・高槻彰良の推察9 境界に立つもの』(角川文庫)
25日 [マンガ]芳崎せいむ 漫画, リチャード・ウー 原作「民俗学者 赤坂弥一郎の事件簿」最終話『月刊アフタヌーン』2023年5月号(講談社)
27日 [マンガ]永椎晃平「スケアリー・キャンパス・カレッジ・ユニバーシティ」第33話「ゼミナール」『週刊ヤングマガジン』2023年4/10号•週刊17号(講談社)
28日 [マンガ](R18)すみやお『即堕ちロリババア』(茜新社、※収録作:「教授と化け猫」)
29日 [小説]芝村裕吏「A Summer Day」第17話「クニ「今の子は変わっているわね」『LOOP8』公式サイト(マーベラス)
4月
4日 [マンガ]夜諏河樹『アンテン様の腹の中 5』(集英社)、近藤憲一『ダークギャザリング 12』(集英社)
6日 [小説]久真瀬敏也『京都怪異物件の謎 桜咲准教授の災害伝承講義』(宝島社文庫『このミス』大賞シリーズ)、天野頌子『よろず占い処 陰陽屋きつね夜話』(ポプラ文庫ピュアフル)
7日 [小説]沖田円『怪異相談処 がらくた堂奇譚』(実業之日本社文庫)
14日 [マンガ]山口譲司 漫画, 木口銀 原案協力『村祀り 17』(芳文社)
26日 [小説]大塚英志『木島日記 もどき開口 上/下』(星海社)
5月
9日 [小説]吉川英梨『警視庁捜査一課八係 警部補・原麻希 グリーン・ファントム』(宝島社文庫 『このミス』大賞シリーズ)
16日 [小説]森らむね 著, 田島列島 原作, 大島里美 脚本『小説 水は海に向かって流れる』(講談社タイガ)
17日 [小説]石川宏千花『化け之島初恋さがし三つ巴 2』(講談社)、蒼月海里『終末惑星ふたり旅』(星海社FICTIONS)
22日 [小説]青崎有吾「アンデッドガール・マーダーファルス 知られぬ日本の面影」『小説現代 2023年6月号』(講談社)
23日 [マンガ]芳崎せいむ 漫画, リチャード・ウー 原作『民俗学者 赤坂弥一郎の事件簿 2』(講談社) / [小説]内藤了『LIVE 警察庁特捜地域潜入班・鳴瀬清花』(角川ホラー文庫)
24日 [小説]森川智喜『動くはずのない死体 森川智喜短編集』(光文社)
26日 [小説]いぬじゅん『十月の終わりに、君だけがいない』(スターツ出版文庫)
30日 [小説]久田樹生 著, いながききよたか,清水崇 脚本『忌怪島〈小説版〉』(竹書房文庫)
6月
1日 [小説]ファミ通書籍編集部 編『LOOP8 公式攻略ガイドブック』(KADOKAWA、※収録作:芝村裕吏「A Summer Day」)
5日 [小説]深森ゆうか『竜を宿す騎士は執愛のままに巫女を奪う』(ソーニャ文庫)
6日 [小説]三津田信三『歩く亡者 怪民研に於ける記録と推理』(KADOKAWA)、江本マシメサ『浅草ばけもの甘味祓い ~兼業陰陽師だけれど、鬼上司と結婚します!~』(小学館文庫キャラブン!)
15日 [マンガ]あまー『よーじょらいふ! 4』(竹書房)
16日 [小説]大島清昭『影踏亭の怪談』(創元推理文庫)
22日 [マンガ]吉元ますめ『くまみこ 19』(KADOKAWA) [ゲーム]オンラインゲーム『ファイナルファンタジーXVI』(スクウェア・エニックス)サブクエスト「タボールの石碑調査」
23日 [ドラマ]『悪鬼(原題:악귀/The Devil)』(STUDIO S、BA ENTERTAINMENT、Disney+)
25日 [小説]どぜう丸『現実主義勇者の王国再建記ⅩⅧ』(オーバーラップ文庫)
29日 [小説]新川帆立『縁切り上等! 離婚弁護士 松岡紬の事件ファイル』(新潮社) / [ドラマ]『疫(えやみ)~ナヒヤサマの呪い~』「第5話 疫(えやみ)~ナヒヤサマの呪い~」(沖縄テレビ)
30日 [マンガ]藤丸豆ノ介 漫画, 友麻碧 原作, あやとき キャラクター原案『浅草鬼嫁日記 あやかし夫婦は君の名前をまだ知らない。 3』(KADOKAWA)、(R18)つくも号『群れ落ちる白い花』(三交社)
7月
4日 [マンガ]モクモクれん「光が死んだ夏 第19話-1」『ヤングエースUP』(KADOKAWA)
5日 [マンガ]景山五月 漫画, 梨 原作「コワい話は≠くだけで。 第17話」『ComicWalker』(KADOKAWA)
14日 [小説]青崎有吾『アンデッドガール・マーダーファルス 4』(講談社タイガ)
21日 [小説]木古おうみ『領怪神犯 2』(角川文庫)、櫛木理宇『ホーンテッド・キャンパス 黒い影が揺れる』(角川ホラー文庫)、大島清昭『最恐の幽霊屋敷』(KADOKAWA)、朝井まかて『類』(集英社文庫)、石川宗生『ホテル・アルカディア』(集英社文庫)
27日 [ゲーム]『流行り神1・2・3パック』(日本一ソフトウェア)
28日 [マンガ]星野之宣『宗像教授世界篇 1』(小学館)、吉川景都「横浜黄昏咄咄怪事」第一話『ヤングキングアワーズ』2023年09月号(少年画報社) / [ゲーム]『なつもん! 20世紀の夏休み』(スパイク・チュンソフト) / [映画]『劇場版 ほんとにあった!呪いのビデオ100』(NSW) / [小説]西條奈加『金春屋ゴメス 因果の刀』(新潮文庫nex)
31日 [アニメ]『ダークギャザリング』「第4話 寶月詠子」(OLM)
8月
2日 [映画][DVD]『ブラッド・チェイサー 呪術捜査線(原題:The Ritual Killer)』(シネマファスト)レンタル開始*1
4日 [マンガ]近藤憲一『ダークギャザリング 13』(集英社) / [小説]夏川草介『始まりの木』(小学館文庫)
9日 [小説]坂木司『アンと愛情』(光文社文庫)、真梨幸子『ノストラダムス・エイジ』(祥伝社)
10日 [マンガ]河内遙『涙雨とセレナーデ 11』(講談社)
12日 [マンガ]露久ふみ「こまどりは、夜の帳」最終回『Dear+』2023年09月号(新書館)
15日 [小説]池田芳正「第6弾カード紹介 第7回 怪異の宴」トレーディングカードゲーム『ゲートルーラー』公式サイト(大遊)
18日 [マンガ]永椎晃平『スケアリー・キャンパス・カレッジ・ユニバーシティ 5』(講談社) / [小説]狭山ひびき『安芸宮島 あやかし探訪ときどき恋』(PASH!文庫)、中西鼎『さようなら、私たちに優しくなかった、すべての人々』(ガガガ文庫)*2
22日 [小説]波摘 著, noprops,黒田研二 原作『青鬼 調査クラブ8 とらわれた仲間を奪還せよ!』(PHPジュニアノベル)
25日 [小説]栗城偲『呪いと契約した君へ』(キャラ文庫)
30日 [ゲーム]スマートフォン向けゲームアプリ『ニューラルクラウド』(サンボーン)イベント「墟上歌」
9月
1日 [小説]ななめ44°『捨てられ勇者は帰宅中~隠しスキルで異世界を駆け抜ける~ 3』(TOブックス)
5日 [マンガ]足鷹高也 漫画, 木古おうみ 原作「領怪神犯 第五章 辻褄合わせの神②」『コミックNewtype』(KADOKAWA)
8日 [マンガ]洋介犬「反逆コメンテーターエンドウさん」第97話『GANMA!』(コミックスマート)
12日 [ドラマ]NHK連続テレビ小説『らんまん』第117回(第24週)「ツチトリモチ」(NHK)
15日 [小説]三津田信三『忌名の如き贄るもの』(講談社文庫)、高田崇史『QED 源氏の神霊』(講談社文庫)
22日 [小説]澤村御影『准教授・高槻彰良の推察EX2』(角川文庫)
27日 [マンガ]相尾灯自 漫画, 澤村御影 原作, 鈴木次郎 キャラクター原案『准教授・高槻彰良の推察 6』(KADOKAWA)、相尾灯自 漫画, 澤村御影 原作, 鈴木次郎 キャラクター原案『准教授・高槻彰良の推察 ファンブック』(KADOKAWA)
30日 [マンガ](R18)蟻吉げん「今様妖綺譚」第一話『サイベリアplus』Vol.17(ぶんか社)
10月
2日 [小説]やまもとふみ『ソレ、迷信ですから~~!!! 悪魔の証明、してみせます!?』(講談社青い鳥文庫)
5日 [小説]百門一新『初恋をこじらせた堅物騎士団長は妖精令嬢に童貞を捧げたい』(ソーニャ文庫)
10日 [小説]小中大豆『アルファ王子の愛なんていりません!』(クロスノベルス)
13日 [小説]内藤了『迷塚 警視庁異能処理班ミカヅチ』(講談社タイガ)
18日 [ゲーム]スマートフォンアプリ『アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ』(バンダイナムコエンターテインメント)期間限定イベント「プラチナスターツアービンゴ~解夏傀儡~」(※これに先行して10月17日に「とある民俗学者の所持品」のメモや「民俗学論文」などの断片的情報がゲーム内(及びTwitter公式アカウント)で公開)
19日 [マンガ]永椎晃平『スケアリー・キャンパス・カレッジ・ユニバーシティ 6』(講談社)
20日 [小説]三國月々子『ナゾノベル 鬼切の子 2 異界から来た少年』(朝日新聞出版)
11月
7日 [小説]久真瀬敏也『大江戸妖怪の七不思議 桜咲准教授の災害伝承講義』(宝島社文庫 『このミス』大賞シリーズ)
16日 [マンガ]山口譲司 漫画, 木口銀 原案協力『村祀り 18』(芳文社)
21日 [小説]小野美由紀『ピュア』(ハヤカワ文庫JA)
24日 [小説]ほしおさなえ『紙屋ふじさき記念館 あたらしい場所』(角川文庫)*3、内藤了『BEAST 警察庁特捜地域潜入班・鳴瀬清花』(角川ホラー文庫)、吉岡暁,曽根圭介,雀野日名子,田辺青蛙,朱雀門出,国広正人『日本ホラー小説大賞《短編賞》集成2』(角川ホラー文庫、※収録作:吉岡暁「サンマイ崩れ」)。
25日 [マンガ]鷹取ゆう『博物館の「怖い話」 学芸員さんたちの不思議すぎる日常』(二見書房)、足鷹高也 漫画, 木古おうみ 原作『領怪神犯 2』(KADOKAWA) / [小説]似鳥航一『佳き結婚相手をお選びください 死がふたりを分かつ前に』(メディアワークス文庫)
29日 [小説]清水朔『奇譚蒐集録 鉄環の娘と来訪神』(新潮文庫nex)
30日 [マンガ]星野之宣『宗像教授世界篇 2』(小学館) / [ゲーム]『Game of the Lotus 遠野大正伝』(Tales & Tokens)
12月
1日 [マンガ]ミツナナエ『久世さんちのお嫁さん 1』(ジーオーティー)、露久ふみ『こまどりは、夜の帳 上/下』(新書館)/ [小説]『小松文芸』第71号(小松文芸発行委員会、※収録作:坂ノ下栄仙「極楽坂物語」)
4日 [マンガ]モクモクれん『光が死んだ夏 4』(KADOKAWA)、近藤憲一『ダークギャザリング 14』(集英社)
5日 [マンガ]吉元ますめ「くまみこ」最終話「クマと少女と田舎と村と」『コミックフラッパー』2024年1月号(KADOKAWA)
8日 [小説]白川紺子『京都くれなゐ荘奇譚 四 呪いは朱夏に恋う』(PHP文芸文庫)、沖田円『怪異相談処 がらくた堂奇譚 2』(実業之日本社文庫)
12日 [マンガ]ルノアール兄弟「少女聖典 ベスケ・デス・ケベス」第109話『別冊少年チャンピオン』2024年新年01月号(秋田書店)
18日 [アニメ]『鴨乃橋ロンの禁断推理』第12話「夜蛇神様殺人事件【前編】」(ディオメディア)
22日 [小説] 高田崇史『猿田彦の怨霊 小余綾俊輔の封印講義』(新潮社)
25日 [アニメ]『鴨乃橋ロンの禁断推理』第13話「夜蛇神様殺人事件【後編】」(ディオメディア)
27日 [小説](R18)ヤスダナコ 著,Escu:de原作『廃村少女 ~妖し惑ひの籠の郷~』(ぷちぱら文庫) / [CD]『THE IDOLM@STER MILLION C@STING 01 解夏傀儡』(ランティス)
とりあえず、現在把握しているところは上記の通り。毎年それなりの数で取りこぼしがあるのだが、そこは今後気づいた時点で追加していこうと思う。
マンガではまず、昨年連載が終了した吉川景都『こまったやつら ~民俗学研究会へようこそ~』の最終第3巻が2月に刊行。7月には、同作者の「横浜黄昏咄咄怪事」が連載を開始しており、こちらは民俗学者ではないが都市伝説を研究する社会学者の男性が主人公で、前作よりオカルト色の強い作風となっている。また、昨年連載を開始した芳崎せいむ 漫画, リチャード・ウー 原作『民俗学者 赤坂弥一郎の事件簿』は商社の人事サラリーマンが民俗学者に転身し下町で起こる事件を解決していくというストーリーだったが、3月に全8話で最終話を迎え、単行本全2巻で完結となった。加えて、吉元ますめ『くまみこ』が12月に最終回を迎え、2013年から10年にわたる連載に幕を下ろした。
また、新しく始まった作品としては、2月に『ハルタ』Vol.101掲載の戸川四餡「黒巫鏡談」は、1937年の朝鮮・京城府が舞台の物語で、失踪した民俗学者が書き残したメモを頼りに怪談作家が日本占領下の朝鮮へ向かうという導入。この作品は全3話の短期集中連載ということだったが、のちに続編の連載が発表された。同じく2月には、星野之宣「宗像教授世界篇」が『ビッグコミック』で連載開始。「宗像教授」のシリーズとしては、読み切り作品を除くと「異考録」以来およそ13年ぶりの連載となる。
新規以外の作品については、澤村御影の小説が原作の相尾灯自『准教授・高槻彰良の推察』のコミカライズ連載が続いていることがまず挙げられる。民俗学専攻の大学生が主人公の今市子『百鬼夜行抄』、民俗学に詳しい本草学者が活躍する山口譲司『村祀り』なども長期連載中。
永椎晃平『スケアリー・キャンパス・カレッジ・ユニバーシティ』では、第33話「ゼミナール」から、伝承民俗学を専門とするイケメン民俗学者・㐂崎珋一教授が登場。着任と同時にカリスマ性を発揮する㐂崎は、主人公が通う鷹陽学園大学で学生たちに怪異譚収集を命じるが、それがやがて陰惨な事件を引き起こす。のち、第35話において、㐂崎が失踪した民俗学者・二村重範の教え子であることが明かされ、怪異にまつわる過去の因縁が描かれていくことになる。㐂崎教授のキャラクター造形には「准教授・高槻彰良の推察」シリーズに代表されるライト文芸的な民俗学者イメージの影響がうかがえる(なお、同作品は当初は『週刊ヤングマガジン』で連載していたが、第35話からは連載媒体を『ヤンマガWeb』に移している)。
景山五月 漫画, 梨 原作『コワい話は≠くだけで。』は、作者をキャラクター化した語り手が毎回さまざまな情報源から怪談を取材していくという形式の連作ストーリーだが、第17話では大学時代に九州地方で民話や風習を研究していたという男性の体験談が語られた。
洋介犬『反逆コメンテーターエンドウさん』では、第97話においてコマ外に「※エンドウさんの本職は民俗学者」という注釈が書き込まれていたが、この裏設定とも言えるような設定が今後も本編に関係してくるかは不明。
変わりダネとしては、ルノアール兄弟『少女聖典 ベスケ・デス・ケベス』第109話で、民股間伝承を採集する第一人者・柳田ペニ男の甥・柳田ペニ之信という柳田國男のパロディキャラクターが登場した。
連載以外では、鷹取ゆう『博物館の「怖い話」 学芸員さんたちの不思議すぎる日常』は、博物館マンガを発表し続けている著者による単行本書き下ろし作品で、民俗担当の学芸員二人を主人公に、博物館で起こる不可思議な話を紹介していくという実話怪談風のストーリー。
また、ミツナナエ『久世さんちのお嫁さん』は民俗学教授と幼な妻の年の差夫婦のラブストーリーで、2015年から電子版が配信サイトで配信されてきたが、このたび全編単行本化となった(全3巻予定)。
BLマンガでは、昼行灯な民俗学教授と教え子の男子大学生が妖怪関係のトラブルを解決していく三国ハヂメ『佐倉叶にはヒミツがある』、山村へ調査に来た民俗学者と囚われの美少年との耽美な交流を描くつくも号『群れ落ちる白い花』、民俗学者の弟と刑事の兄の双子が不審死事件を追って山奥の小村へ捜査に向かうという露久ふみ『こまどりは、夜の帳』などの作品が単行本化された。
男性向けの成人マンガでは、すみやお「教授と化け猫」(『即堕ちロリババア』所収)、蟻吉げん「今様妖綺譚」(『サイベリアplus』)など、民俗学研究者の男性主人公と猫や狐といった動物の妖怪との組み合わせが目立った。
また、本当は民俗学者ではないのだが作中でキャラクターが便宜的に民俗学者を名乗るというパターンがある。実際に民俗学者ではない、あるいは民俗学者かどうか不明だが、少なくともキャラクター本人は民俗学者を自称している、あるいは民俗学者でないのは自明だが不慣れな土地での聞き込みのためにその場に限って民俗学者を名乗っているというパターンである。
モクモクれん『光が死んだ夏』では、謎のサングラスの青年・田中が「民俗学者」を自称して主人公に接触しているが、これはその前後の描写からおそらく霊能力者が怪異の情報を得るために民俗学者を装っているという展開かと想像される。また、足鷹高也 漫画, 木古おうみ 原作『領怪神犯』でも、「第五章 辻褄合わせの神」において、怪異を調査する主人公らが民俗学者を装って地元住民から情報を聞き出す場面があった。
これは、実はオカルト系のマンガではたびたび見られるもので、ある種の定番のパターンでもある*4。小説では、谷尾銀『ゆるコワ! ~無敵のJKが心霊スポットに凸しまくる~』で似たようなシチュエーションがあった。
他には、キャラクターに関してではないが、『本当にあった笑える話』2023年10月号で連載開始した三ノ輪ブン子「ただのうわさです」は、民俗学者の飯倉義之が原案協力を担当している作品である。
小説では、大塚英志『木島日記 もどき開口』が星海社から上下巻で復刊し、2022年の『木島日記 うつろ舟』に続く刊行となった。また、2月に櫻田智也『蝉かえる』が、6月に大島清昭『影踏亭の怪談』が、8月に夏川草介『始まりの木』がそれぞれ文庫化した。12月には、異端の民俗学者・小余綾俊輔が活躍する高田崇史「小余綾俊輔の講義シリーズ」の第2作目『猿田彦の怨霊 小余綾俊輔の封印講義』が刊行された。
民俗学者キャラクターが登場する小説は、全体の数で見ると、やはりライト文芸のジャンルで顕著な傾向にある。特に2023年は前年も含めて作品のシリーズ化が目立った。角川文庫の澤村御影「准教授・高槻彰良の推察」シリーズ、小学館文庫キャラブン!の柊坂明日子「一教授はみえるんです」シリーズ、宝島社文庫の久真瀬敏也「桜咲准教授の災害伝承講義」シリーズといった民俗学者が主役のシリーズのほか、角川ホラー文庫の芦花公園「佐々木事務所」シリーズ、新潮文庫nexの萩原麻里「呪殺島」シリーズ、PHP文芸文庫の白川紺子「京都くれなゐ荘奇譚」シリーズ、実業之日本社文庫の沖田円「怪異相談処 がらくた堂奇譚」シリーズなどの民俗学者キャラクターが重要なサブキャラの位置にある作品も多い。
児童文学においては、PHPジュニアノベルの波摘「青鬼 調査クラブ」シリーズではオカルト民俗学者が引き続き登場、朝日新聞出版ナゾノベルの三國月々子「鬼切の子」シリーズでは主人公のいとこで民俗学を研究する大学院生が登場している。講談社青い鳥文庫のやまもとふみ『ソレ、迷信ですから~~!!! 悪魔の証明、してみせます!?』は科学オタクの中学生主人公が民俗学オタクのイケメンクラスメイトと身近な迷信を紐解いていくストーリー。
また、これは小説に含めてよいのかどうか微妙だが、『ゲートルーラー』公式サイト(大遊)に掲載された「第6弾カード紹介 第7回 怪異の宴」(記事:池田芳正)は、本来は新作のトレーディングカードの紹介を目的としたコラム記事だがこの回はなぜか民俗学者の主人公がカードゲームに登場する妖怪キャラクターたちと戦う小説形式の記事になっていた。
アニメでは、『ダークギャザリング』「第4話 寶月詠子」(7月31日放送)では、花澤香菜演じるヒロイン寶月詠子が民俗学専攻であることが語られた。この回は、彼女が受講する都市伝説の講義の担当者(声:神尾晋一郎)が講義の中で呪いのビデオを上映するが本当に悪霊を呼び起こしてしまう……という話。
『鴨乃橋ロンの禁断推理』第12話「夜蛇神様殺人事件【前編】」及び第13話「夜蛇神様殺人事件【後編】」(12月18日、25日放送)は、主人公の探偵と刑事が失踪した民俗学者を捜索しに山梨県の村に行くというエピソードで、失踪した民俗学者シェパード・ファイアを小西克幸が演じた他、蛇神信仰を調査するために村に滞在していた民俗学者・室井(声:真木駿一)も登場した。
『ダークギャザリング』も『鴨乃橋ロンの禁断推理』も原作マンガのストーリーをほぼ忠実になぞっているが、『鴨乃橋ロンの禁断推理』のシェパード・ファイアは、マンガでは名前が不明で、アニメで初めてフルネームが設定された。
他に出てきたネタを拾っていくと、『アリス・ギア・アイギス Expansion』「第4話 お祭り騒ぎだヨ!成子坂!(準備編)/お祭り騒ぎだヨ!成子坂!(当日編)」(4月25日放送)では、民俗学者キャラクターは登場しないものの、登場人物の一人である百科文嘉(声:石川由依)が「民俗学者の柳田国男によれば~」と民俗学的な知識を引き合いにしてお祭りで売る団子を解説するセリフがあった(アニメで柳田国男の名前が出る機会は非常にめずらしい)。また、『ホリミヤ -piece-』page.6「お泊り会」(8月5日放送)では、主人公の友人の仙石翔(声:岡本信彦)の自室の本棚に『民俗学辞典』というタイトルの本が並んでいる様子が映った。仙石のセリフでは「父さんの本とかあるんだぞ」と言っており、本の見た目は東京堂刊行の同名書籍に酷似していた。
ゲームでは、オンラインゲーム『Sailing Era(セーリング エラ)』が1月に配信開始、プレイアブルキャラクターとして異国の商人と取引をする女性民俗学者キャラクターが選択可能。このゲームは、大航海時代を題材にしており主人公は4人の船長キャラクターから選択可能だが、そのうち民俗学者キャラクターは中国の商人の一族出身の18歳の女性という、フィクションの民俗学者の設定としては特異。
スマートフォン向けゲームアプリ『IdentityV 第五人格』では、1月の春節イベント2023「戯楽で旧年を辞し 粉墨で新年を描く」のイベント報酬に「小説家」の新衣装「民俗学者(民俗作家)」が実装(イベント7日目のログインボーナス)された。
7月発売のNintendo Switch用ゲームソフト『なつもん! 20世紀の夏休み』では、主人公の友人の父親で天狗伝説を調べている谷地頭という民俗学の教授が登場。谷地頭教授の家では、クエストを達成することで、ざしきわらしの少女と出会うことができる。
8月には、スマートフォン向けゲームアプリ『ニューラルクラウド』のイベント「墟上歌」(8月30日~9月20日)において新キャラクター「蔵音」(声:ゆきのさつき)が実装され、元は民俗学の研究用に開発された人形だったが自ら戦闘に参加したという設定でお嬢様風の山の手言葉と稲川淳二と廓言葉を混ぜたような独特の口調で喋る*5。
10月に開催されたスマートフォンアプリ『アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ』の期間限定イベント「プラチナスターツアービンゴ~解夏傀儡~」(10月18日~25日)では、劇中劇の「彼ハ誰ノ彼岸」において徳川まつり(声:諏訪彩花)が「学者」を演じるという設定で、これに先行して10月17日に「とある民俗学者の所持品」のメモや「民俗学論文」などの断片的情報がゲーム内(及びTwitter公式アカウント)で公開された。また、12月には該当の劇中劇を収録したキャラクターソング&ドラマCDも発売された。
また、11月30日発売の『Game of the Lotus 遠野大正伝』は、岩手県遠野市の地域振興のために、ふるさと納税の返礼品として制作・販売されている着せかえNFTで、『遠野物語』を題材としたキャラクターやストーリーを提供するもの。2022年の第1弾に続く第2弾の今回は、「柳田國男」や「佐々木喜善」といった実在の民俗学者をモデルにしたキャラクターが登場する。
また、正確には「民俗学者」ではないが、オンラインゲーム『ファイナルファンタジーXVI』で6月に発生したサブクエスト「タボールの石碑調査」では「民族学者」の老人ミロシュが登場した。
映画では、2月公開の『呪呪呪 死者をあやつるもの』は、2020年のテレビドラマ『謗法~運命を変える方法~(原題:방법)』(tvN)のシリーズ作品で、前作に引き続き呪術に詳しい民俗学の教授をコ・ギュピルが演じる。
7月公開の『劇場版 ほんとにあった!呪いのビデオ100』でも民俗学研究者の男性が登場した。
8月にレンタルを開始した『ブラッド・チェイサー 呪術捜査線』は日本劇場公開なしのDVD・配信作品。この作品では、モーガン・フリーマンがアフリカの呪術に詳しい大学教授を演じているものの、DVDの商品説明では「アフリカ民俗学の権威」となっているが、そもそも映画本編では「アフリカ研究」の教授としか説明されない。しかし、猟奇的な殺人事件が起こり、現場の痕跡から学者が呪術的な儀式の痕跡を読み取り、それを元に刑事が捜査を進めるという流れは、他作品のオカルト民俗学者と類似のパターンにあると言える。
また、6月に公開された田島列島の同名マンガが原作の映画『水は海に向かって流れる』では、民俗学者ではないが世界中を旅する文化人類学者の大学教授を生瀬勝久が演じた。
ドラマでは、2月にAmazon Prime Videoで『A2Z』全10話が配信されたが、これは山田詠美の同名小説のドラマ化で、木南晴夏が主人公の親友ポジションの民俗学者を演じた。
6月からDisney+で配信された韓国ドラマ『悪鬼』全12話では、霊能力を持つオカルト民俗学者をオ・ジョンセが演じている。
ホラードラマとお化け屋敷が連動した沖縄ホラープロジェクト2023『疫(えやみ)~ナヒヤサマの呪い~』では、6月29日に放送されたドラマ「第5話 疫(えやみ)~ナヒヤサマの呪い~」で、沖縄の特撮ドラマなどにも出演している玉代勢圭司が怪異に巻き込まれる地元の民俗学者・河上を演じた。
NHK連続テレビ小説『らんまん』第102回(第21週)「ノジギク」(8月22日)では、中田青渚演じる田邊聡子の「いえ、柳田の家には帰りません」というセリフがあったが、この「柳田の家」は聡子のモデルとなった矢田部順の実家である柳田家を指すと思われ、これは民俗学者・柳田国男が養嗣子となった家でもあった。また、第117回(第24週)「ツチトリモチ」(9月12日)では、神木隆之介演じる主人公の植物学者槙野万太郎のもとに南方熊楠(※配役なし)から手紙と植物標本が届くというエピソードが描かれた。
また、CMでは、2月に、株式会社ワールドパーティーの傘ブランド「Wpc.(ダブリュピーシー)」の2023年春夏ビジュアルとスペシャルムービー『Wpc.2023 春夏物語 雨と傘と蛙亭』がYouTube等で公開され、これはサスペンス映画の予告編風のコマーシャル映像で、吉本興業所属のお笑い芸人「蛙亭」のイワクラが呪われた館にまつわる都市伝説を検証する民俗学者を、同じく「蛙亭」の中野周平がその助手を演じた。
上記の一覧リストには記載しなかったが、ここで少し演劇の分野にも目を向けてみたい。いくらかネットの情報を見てみると、近年上演されている国内の演劇においても、どうやら民俗学者キャラクターはそこここに頻出しているらしい。2023年の作品では、ダンスカンパニー「DAZZLE(ダズル)」のイマーシブシアター「百物語 - 零レ桜 -」(3月10日~4月9日、東京 表参道)「百物語 - 君影草 - 」(5月26日~6月4日、京都 五條会館)、排気口 / 中村ボリ企画公演「人足寄場」(4月5日~9日、東京 荻窪小劇場)、タカハ劇団 第19回公演「おわたり」(7月1日~9日、新宿 シアタートップス)、Jungle Bell Theater 2本立て公演「夜行万葉録・戌」「おとぎ夜話・寿」(8月9日~14日、東京 オメガ東京)、座・シトラス アナザー「きさらぎミッドサマー弐式」(12月17日、東京 ジョイジョイ ステーション)などの公演において民俗学者キャラクターが登場した。これらの作品では、民俗学者は霊媒師や霊能力者とともに物語に登場していたり、ストーリーも多くが怪談や百物語、都市伝説などを題材にしている。演劇においても民俗学者キャラクターの描かれ方はかなり通俗的なオカルト民俗学のイメージが濃い傾向があるものと思われる。
ここからはせっかくのなので少し感想を述べてみるが、『呪呪呪 死者をあやつるもの』、『ブラッド・チェイサー 呪術捜査線』などの例にもあるように、民俗学者あるいは文化人類学者が警察と協力してオカルト事件を捜査するというドラマのパターンは日本のみならず、韓国や欧米においてもままあるようだ。このような作品がいくつも出てくる背景として連想されるのは、『ミッドサマー』をはじめとした昨今のフォークホラーの流行だ。風間賢二がマネル・ロウレイロ『生贄の門』(新潮文庫)の解説で書いているように、ミステリー仕立てのフォークホラーは近年の流行となっているが、一方で「フォークホラー」という言葉は日本ではまだなじみがない状況にある*6。フォークホラー作品には必ずしも民俗学者キャラクターが登場するわけではないが、民俗や民俗学、民俗学者をオカルトと絡めて描くフィクションは映画などでもここ数年で目立っている一方で、これらの描かれ方については、日本国内においてはいまだじゅうぶんに語られているとは言い難い。
このあたり、アダム・スコヴィルのFolk Horror : Hours Dreadful and Things Strange(リヴァプール大学出版局、2017年)の翻訳が出るか、『ユリイカ』かどこかでフォークホラー特集が組まれるかすれば、ある程度は解消される部分があるのではないかというようなことをぼんやりと考える。少なくとも現在、「因習村」などのネットスラングで括られている範囲については、いくらかは見通しがしやすくなるのではないか……。
さて、2024年の作品でわかっているところでは、ComicWalkerあらためカドコミで連載中の狐面イエリ 漫画, 芦花公園 原作『異端の祝祭』では、原作通りであれば民俗学者が登場予定。足鷹高也 漫画, 木古おうみ 原作『領怪神犯』でも、このまま連載が続けば原作にある女性民俗学者がメインで登場するパートが始まるものと思われる。ゲームでは、『青十字病院 東京都支部 怪異解剖部署』(フロシキラボ)がいよいよリリース予定とのことで今後の展開に期待したい。
現時点でまとめられる情報は以上のような感じ。訂正や追記すべき箇所があれば随時更新していくのでご容赦願いたい。また、もし記事の中でお気づきの点などあればどうかどんどんご指摘いただければ幸いである。では、今回はそんなところで。
*1:アメリカではレッドボックス・エンターテインメント, スクリーンメディアから2023年3月10日リリース、日本版はTCエンタテインメントから2023年10月4日発売。
*2:民俗学者キャラクターは登場しないが中山太郎をもじった民俗学者の著書を参照する場面がある。
*3:民俗学者キャラクターは登場しないが長野県飯田市の柳田國男館が舞台の一部となっている。
*4:過去の作品だと、ジョージ朝倉『溺れるナイフ』(講談社、2005~17年、単行本全17巻)の蓮目匠、鈴木ツタ『この世 異聞』(リブレ出版、2006~13年、単行本全7巻)の真川勇一、西尚美「あかりとシロの心霊夜話 見送りの崖」(『あかりとシロの心霊夜話 13巻』Bbmfマガジン、2011年)の民俗学部教授を名乗る児童ポルノ密売業者、児玉樹『まほマほ』(角川書店、2012~13年、単行本全3巻)の物部清太郎などの例がある。
*5: 「蔵音さん本日実装!民俗学を専攻する比類なき口達者ということで、お嬢様言葉の由緒とも呼べる東京山の手言葉+稲川淳二御大の語り部+廓言葉、これらを盛り込んだ本人同様大変クセのある口調を付与してみました。複雑な要望にお応え頂いた役者様の演技は芸術というほかありません、ぜひご堪能ください!」( ずんこ @Zunko_lalala 午後3:13 · 2023年8月30日 https://twitter.com/Zunko_lalala/status/1696768139705364636?s=20 )
*6:風間賢二「フォークホラーとしての傑作ミステリー」、マネル・ロウレイロ 著,宮﨑真紀 訳『生贄の門』新潮文庫、2023年、504頁
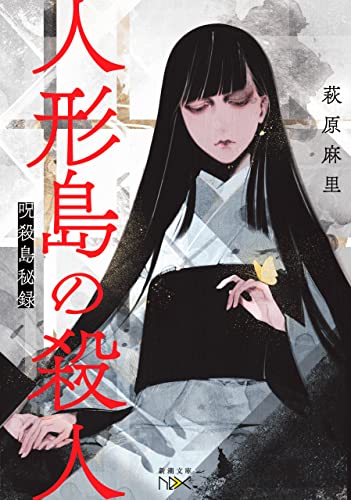





























![八月のかりゆし [DVD] 八月のかりゆし [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/21X98NTZB8L._SL500_.jpg)

![単騎、千里を走る。 [DVD] 単騎、千里を走る。 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/419fVpGAuTL._SL500_.jpg)
![奇談 プレミアム・エディション [DVD] 奇談 プレミアム・エディション [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W31HTKFAL._SL500_.jpg)
![エクスクロス 魔境伝説 [DVD] エクスクロス 魔境伝説 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51xGx5V4-lL._SL500_.jpg)











![Kavkazskaya plennica, ili Novye priklyucheniya Shurika (RUSCICO) (Die kaukasische Gefangene oder Die neuen Abenteuer Schuriks) (Engl.: Kidnapped ... New Adventures) - russische Originalfassung [Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика] Kavkazskaya plennica, ili Novye priklyucheniya Shurika (RUSCICO) (Die kaukasische Gefangene oder Die neuen Abenteuer Schuriks) (Engl.: Kidnapped ... New Adventures) - russische Originalfassung [Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Qe5T00RHL._SL500_.jpg)

![ルール デラックス版 [DVD] ルール デラックス版 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/210PXWM3F5L._SL500_.jpg)

![獣の戯れ [DVD] 獣の戯れ [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51CEJGfGTbL._SL500_.jpg)
![The Savage Hunt of King Stakh / Dikaya Okhota Korolya Stakha by Boris Romanov [DVD] The Savage Hunt of King Stakh / Dikaya Okhota Korolya Stakha by Boris Romanov [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51NXBvfze1L._SL500_.jpg)
![ガメラ巨大生物審議会 [DVD] ガメラ巨大生物審議会 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/31QQWHRR3HL._SL500_.jpg)
![銀の男 六本木ホスト伝説 [DVD] 銀の男 六本木ホスト伝説 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51OmCTZzckL._SL500_.jpg)


![The Whisperer in Darkness [Blu-ray] The Whisperer in Darkness [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51XAsNiaP7L._SL500_.jpg)




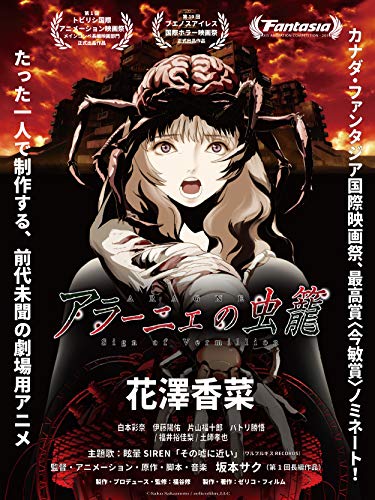


![Shirley [DVD] Shirley [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51kZn3A5TDL._SL500_.jpg)
![いとみち(特典DVD付き2枚組) [Blu-ray] いとみち(特典DVD付き2枚組) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51w7SaV8cYL._SL500_.jpg)

![キャラクター 通常版 [DVD] キャラクター 通常版 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51E8oyn1yrL._SL500_.jpg)































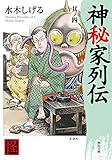

![河童のクゥと夏休み [DVD] 河童のクゥと夏休み [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51+bqWxiipL._SL160_.jpg)

![神霊狩/GHOST HOUND 1 [DVD] 神霊狩/GHOST HOUND 1 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/5192oBABmCL._SL160_.jpg)
![迷家-マヨイガ-1 [DVD] 迷家-マヨイガ-1 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/61KT3dPWojL._SL160_.jpg)
![トリック(2) [DVD] トリック(2) [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/41EY6GN9EKL._SL160_.jpg)





